桜の頃になると、思い出す味がある。
40年ほど前。九州を離れ、進学のために上京することになった。
私は有頂天だった。厳しかった父親の管理下を離れ、夢の一人暮らしが始まることに心を奪われていた。そこにあった両親の思いを顧みる余裕など、まったくなかった。
東京に送り出した荷物は、布団袋と数箱の段ボール。その荷物を追いかけるように、夜行寝台に乗り込んだ。駅まで送りにきてくれた家族の表情に少しだけ心は湿っぽくなったが、汽車が久留米を過ぎる頃には、チクチクする思いは東京への期待にかき消されていた。
新居は目黒の4畳半の古いアパートだった。風呂なし、トイレ共同。小さい流しとガスコンロ置場はあったが、部屋の入口の土間の脇に位置していたので、流しに立つ時には靴を履く必要があった。しかし、そんなことはどうでもよかった。どんなに古くても、すべてがリセットされ、すべてが新しく始まる場所として、私にはその部屋が輝いて見えた。
田舎から送った荷物をほどいていると、わずかの食器と鍋が入った段ボールの中から、小さな銀色の缶が出てきた。ふたを開けてみると、中には〝いりこ〟が入っていた。
「前の夜に、水に浸けとけばいいんだから」。
母が荷造りの時にそんなことを言っていたのを思い出した。しかし、1人暮らしを始めたばかりの18歳男子が味噌汁を作るわけもなく、ましてやいりこで出汁をとるはずもない。私は、母親の言葉を閉じ込めるように、缶を段ボールに戻した。
東京での生活は想像以上に刺激的で、昼も夜もなく、バイトと酒と映画に明け暮れる毎日が続いた。それから何度か引越しを繰り返したが、銀の缶の入った段ボールは封を開けることもないまま、新しい部屋へと持ち越されていった。
東京での暮らしも8年ほどが過ぎ、結婚することになった。独身暮らしにピリオドを打つため、溜まりに溜まったガラクタを処分する時が来た。その中に、あの段ボールもあった。
1人暮らしを始めた時に開けたきりだった缶のふたを恐る恐る取ると、いりこは緑と白のカビを全身にまとっていた。その瞬間、ツンと鼻の奥を突き上げるものがあった。
「ごめん、母さん」。
いりこの入った缶を段ボールに詰める母の思いが、その時、やっと心に届いた。
私は40歳を前に東京を離れ、家族と共に九州へ戻った。
わが家で作る味噌汁の出汁は、もちろんいりこだ。母は一昨年他界したが、毎日味噌汁を飲むたびに、あの時の母の言葉を思い出す。前の夜にいりこを水に浸す気持ちの余裕がいかに大切か、思い知る日々である。特に桜の時期は、目黒の部屋と段ボールと銀色の缶に、腹を取っていないいりこのほろ苦い味が重なって、少しだけ胸が苦しくなる。
今年は、娘が大学進学。いりこの味をどう伝えるか、思案中である。
(九州の食卓2014年春号より)
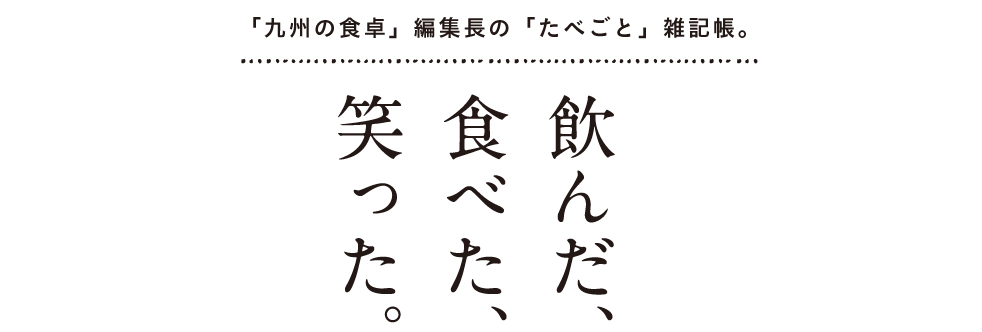



コメント