雑誌「九州の食卓」でも、地産地消や身土不二という言葉をよく使っていました。漢字ばっかりで、なんだか難しそうな言葉ですが、自分が暮らす土地で生まれ育った食材を食べることが体にいいという考えは、難しい理屈は別にしても本能的に納得がいく気がします。
宮崎県綾町に暮らす薬膳料理家の郷田美紀子さんは、極寒の地に住むエスキモーが生肉を食べたり、極度な乾燥地帯に暮らす人たちに乳製品が欠かせなかったり、熱帯では豊富なくだものが育ち、それが地元の人たちに大量に食されていることはすべて必然の結果であると話していました。そして、極寒でも熱帯でもなく、多湿な気候の日本で同じような食事をすると、体に不調をきたすことがあると何度も繰り返しました。「時々ならいいのよ。乳製品もくだものもお肉も。でも、毎日、食べすぎるのは日本人の食事としてはお勧めできないということ。昔の日本人は食べてなかった食材ばかりでしょう」。
郷田さんは実にチャーミングな女性。ベイビーフェイスで、万人を包み込むような柔らかい笑顔がとても魅力的な方です。宮崎弁を交えながら、抑揚のあるイントネーションでこんな話をされると「そうだよなぁ」と納得してしまいます。郷田さんは薬剤師でもあり、薬局の隣で食事処も営まれていて、運が良ければお話しを聞くこともできます。食養に興味のある方は、ぜひ訪ねてみてください。そこで出会える料理と郷田さんの笑顔は、きっと幸せな気持ちにしてくれるはずです。(https://mikiko-gouda.jimdofree.com)

でも、理屈ではわかるのですが、私はしたたる肉汁を見るとよだれが出てしまいます。おいしいチーズがあるとワインを抱え込んでしまいます。シャインマスカットは無限に食べられそうです。さて、ここをどう考えるかです。
これを冒頭の地産地消という視点で考えてみましょう。私が暮らしている九州は、食材に関しては天国のような島です。肉、乳製品、くだものについても多種、大量に生産されています。豚の飼育頭数は鹿児島がダントツの全国1位、宮崎が2位。ブロイラーは1位が宮崎、2位鹿児島、7位佐賀、8位熊本、10位長崎と、ベスト10に九州の5県が入っていて、そのシェア47.9%。鶏肉の半分は九州で生産されているのです。牛肉の第1位は北海道ですが、2位は鹿児島、2位は宮崎、4位が熊本、8位に長崎が入っていて、4県で31.7%のシェアです。とにかく、九州は畜産王国なのです。
一方、乳牛はというと、これは北海道が全国の6割を占める圧倒的産地ですが、ここでも熊本が全国3位の生産量を誇っています(以上、平成32年の農林水産省「畜産統計」より)。
また、くだものも福岡のいちご「あまおう」や熊本の柑橘「でこぽん」など、全国に知られるブランド品をはじめ、ぶどう、もも、なし、びわ、いちじく、スイカ、柿など、実に豊富な種類が栽培されています。つまり、九州で暮らす人にとっては、わざわざ海外や遠くの地で生産された肉やくだものに頼らなくても、身近に豊富にあるということです。好きなものが、全部地産地消で賄えるということになります。
「じゃあ、食べてもいいんじゃん」。まあ、私自身への言い訳も含めて、そういうことにしておきましょう。でも、ほどほどにということです。
では、「ほどほどってどのくらい?」でしょうか。郷田さんは、これを「ハレの日」の食事と「ケの日」の食事という言葉で表現していました。「ハレの日」とは、お祝い事や節句、お祭りなどの特別な日。これに対する普段どおりの日常が「ケの日」です。着飾って、ご馳走を食べるのが「ハレの日」だとすれば、いつもと変わらない質素な食事を食べるのが「ケの日」ということになります。このイメージでいくと、「ハレの日」は多くても月1回という感じでしょうか。でも、ご馳走食べるのが、月1回では苦しい。もう少し、増やしたい!
というわけで、私は週末を「ハレの日」に制定しています。コアは土日ですが、ときどき金曜日も仲間入りします。最近はコロナもあって皆無ですが、ウィークデイに飲み会や祝い事などが入れば、週末の日数を調整します。郷田さんが「毎日がハレの日の食事じゃダメなのよ」と言っていたのを無理に思い出して、毎日ではないことを言い訳にしています。皆さんも、ご自分の体調や健康状態、食の好みに合わせて「ハレの日」の頻度を決めてみてください。
さて、地産地消に話を戻すと、肉や乳製品、くだものだけでなく、野菜や魚も九州には豊富にあります。近くで採れているということは新鮮だということでもあります。流通にコストがかからず、輸送トラックからの二酸化炭素の排出も少なくてすみます。いいことずくめです。輸入より国産、県外よりも県内産、生産者不明よりも知り合い産。そんな観点で選ぶと、食材もよりおいしくなったような気がします。おいしさは科学的な成分構成よりも、信頼が元になった安心感に感じるものだと思っています。理想は自分で食材を作ること。それができなければ、知っている人が作ったものを選ぶ。それも無理なら、地元のものを選ぶ。
おいしいものは、足元にあるのです。
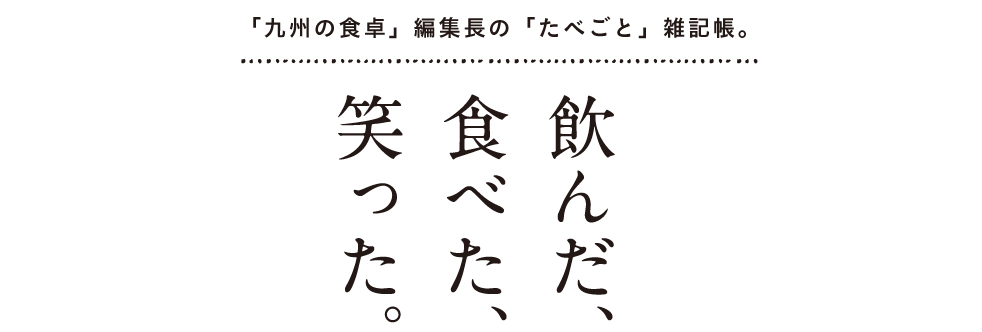


コメント